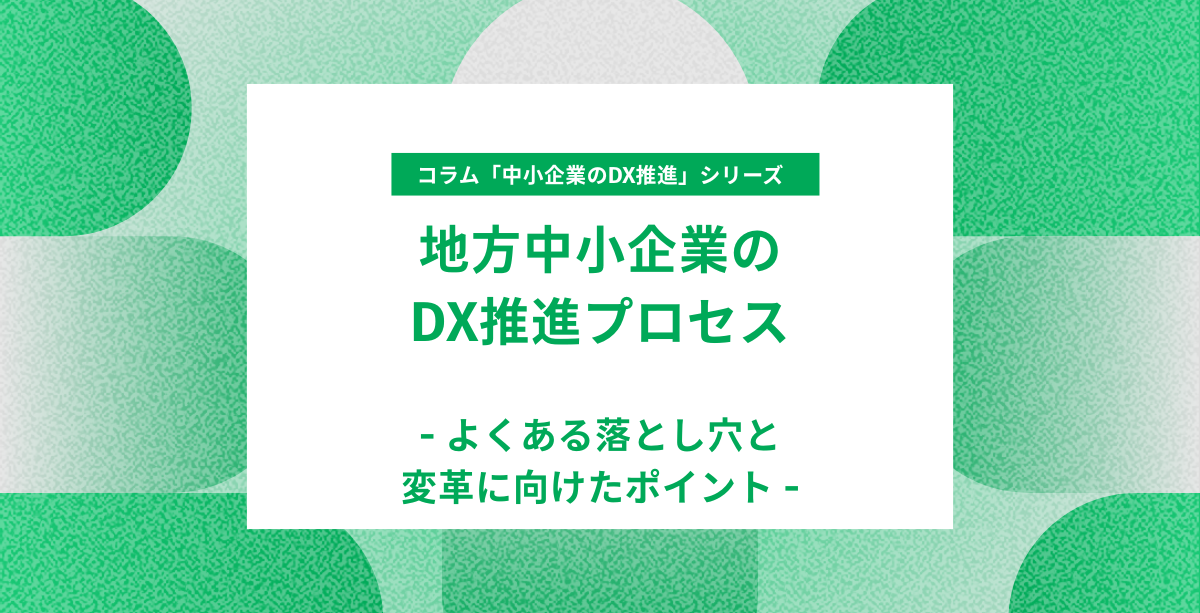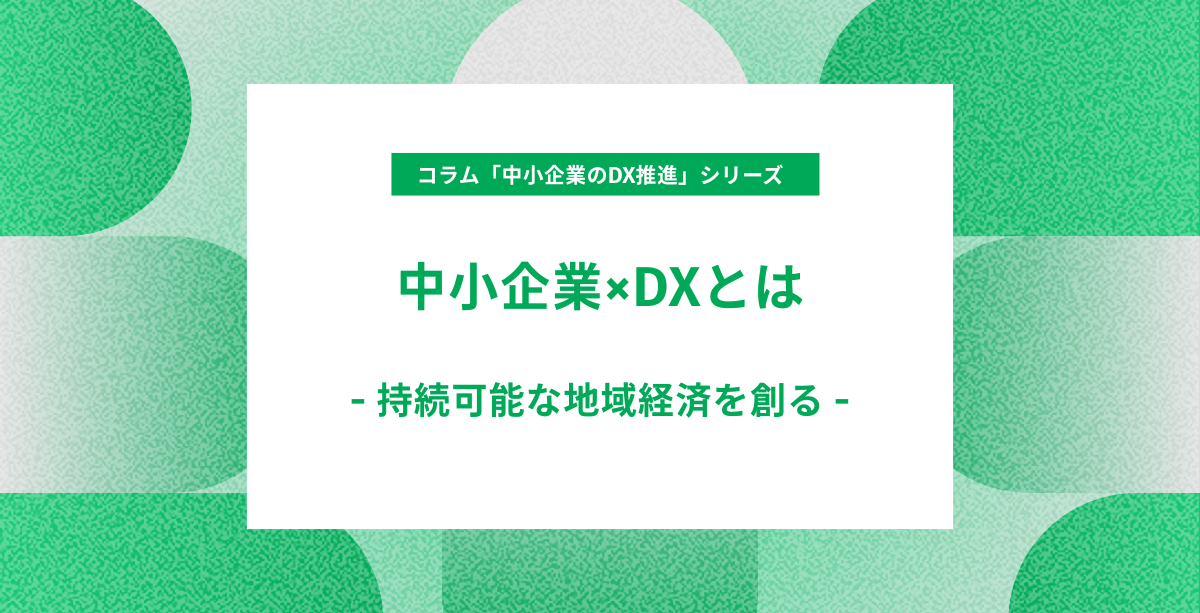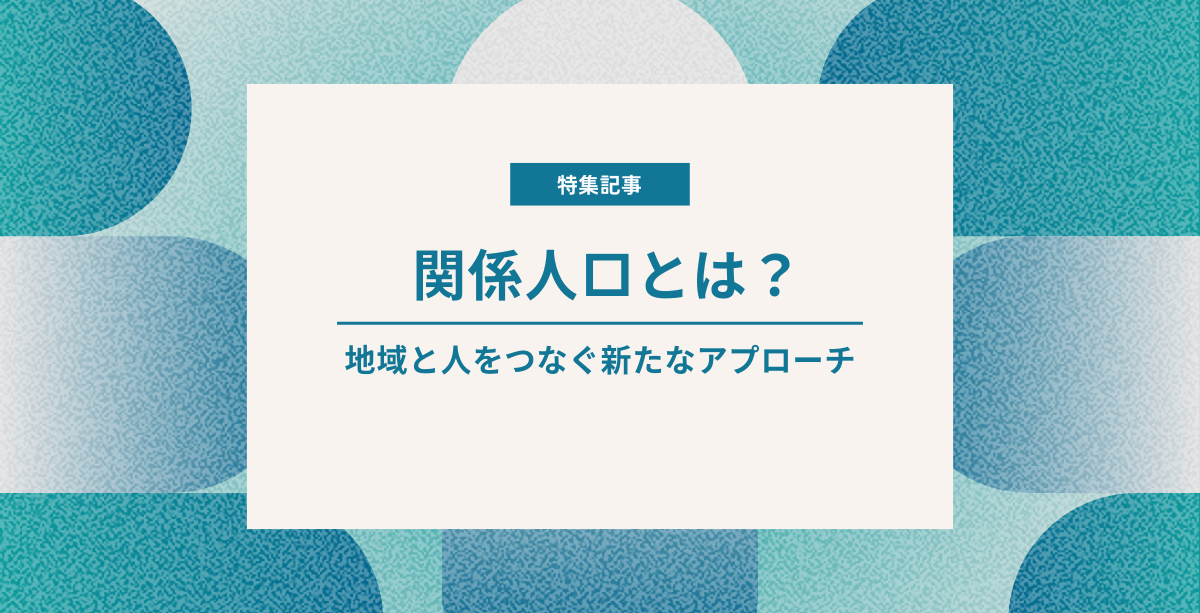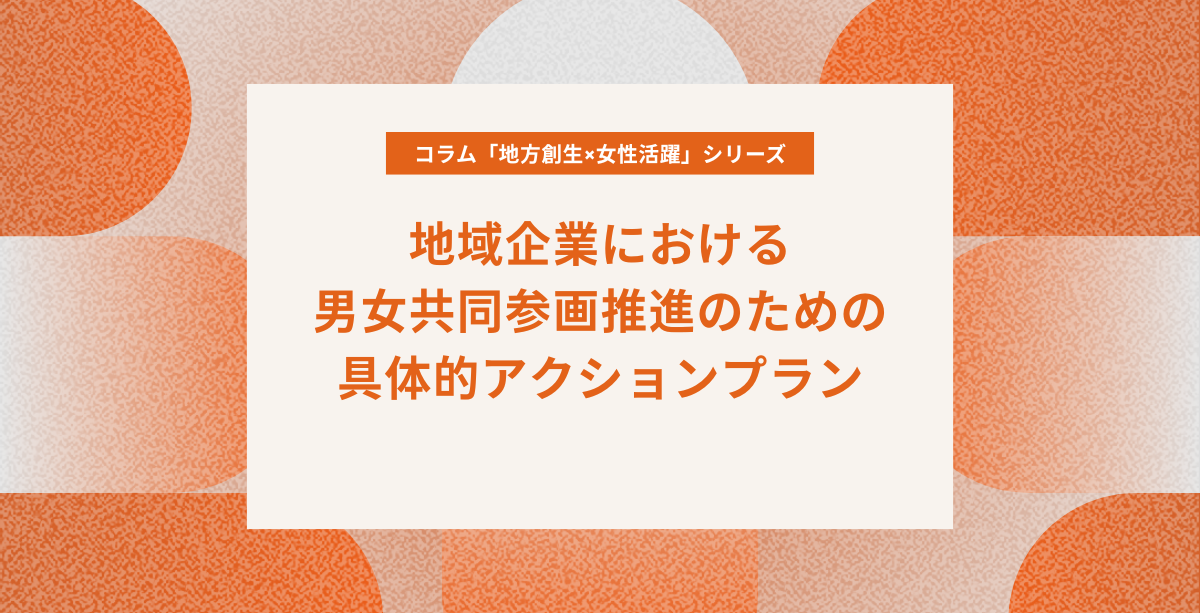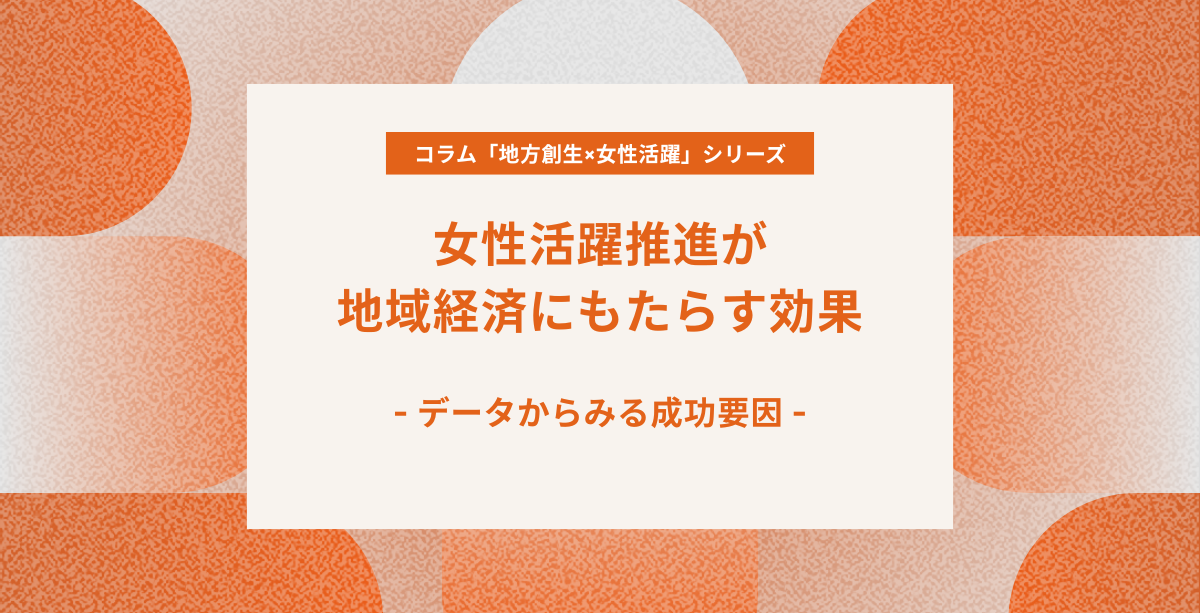日本全体が慢性的に抱えている課題である少子高齢化。
団塊世代の高齢化とともに少子化が進行すると生産年齢人口が減少する一方で、親の介護により限られた時間・場所でしか働くことができない人が増えてきます。
特に地方は既に人口が少なく、高齢者の割合が都市部に比べて高い傾向にあるので、今後人材不足はさらに深刻になっていきます。
そんな中で地域の企業、まちを維持していくためには企業や自治体が積極的にデジタル技術を活用し、少ない人材や時間でこれまでと同じもしくはそれ以上の状況を作っていく必要があります。
そこで、本コラムではデジタル技術を活用した業務改革はどのように段階が分かれていて、どのように進めていくべきなのかについて解説していきます。
DXの段階とは
デジタル技術の活用による業務改革には幾つかの段階があります。
- 段階1「未着手」:デジタル化(デジタル技術を用いた単純な省人化、自動化、効率化、最適化)が全く未着手の段階
- 段階2「デジタイゼーション」:業務の一部の作業をデジタルに置き換え始め、事務作業の負担が減りコスト削減の効果が見え始める段階。この段階では、業務個別のデジタル化にとどまる。
- 段階3「デジタライゼーション」:一部の業務にとどまらず業務プロセス全体をデジタル化、業務の改善を行っている段階。
- 段階4「デジタルトランスフォーメーション(DX)」:デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化なども変革していく段階
※広義のデジタルトランスフォーメーション(DX)は段階1から段階4までの全ての取組を総称する概念ですが、狭義のデジタルトランスフォーメーション(DX)は段階4の取組のみを指す概念となります。何を指してDXと呼ぶかはその都度確認していくことが重要です。
段階2、段階3はデジタル技術により業務の効率化を図ることで、主に「コスト削減による利益率の向上」を狙う段階である一方で、段階4は新たな商品、サービスの提供、ビジネスモデルの開発を行うことで「売上高の向上」を狙う段階です。
言い換えれば、段階2、段階3は、既存事業の継続を前提とした際に、人口減少とともに顧客の数も減っていくだろうという仮説があるため、デジタル化で効率化してもいつかは利益が確保できなくなってしまう可能性があります。
一方、段階4のDXは新たなチャネル開拓やサービス開発を通じて新たな市場開拓につなぎ、既存事業にはない収益を発生させる投資行為になります。将来的な組織存続のためにDXを経営戦略に取り入れることは重要です。
事例で具体的にイメージしてみましょう。
【株式会社髙梨製作所(山形県河北町)の事例】
株式会社髙梨製作所は熱硬化性樹脂・熱可塑性樹脂の精密成形、金型の設計、製作を行っている従業員17人の企業です。
全社的なDX推進体制の構築により高効率な無人稼働と働き方改革を同時に成し遂げました。
段階的にDXを達成している好事例です。

【岩舘電気株式会社の事例】
岩舘電気株式会社は病院やショッピングセンターなどの電気設備の施工を行っている従業員74名の企業です。
社内のあらゆる情報をデジタル化、可視化を行い、売上・利益の向上だけでなく労働環境の改善にも取り組んでいます。


出典:「情報通信白書 for Kids」(総務省, 2025年7月23日参照)
なぜ「地域×中小企業」のDXが今、必要なのか
日本全体の人口が減少する中、特に、地方の少子高齢化や人口減少は大きな課題です。
地域人口は地域企業の担い手であったり、消費者であったりするため、多くの地域企業にとっては厳しい状況であると言えます。
そのような状況において人手不足を解消し、消費者に利便性をもたらしファンを増やすためにも「デジタル化」や「DX」は有効なことがあります。
地理的なデメリットを乗り越え、むしろ都市部よりもあらゆるコストが相対的に低い地域だからこそのメリットを活かしたビジネス構想も可能かもしれません。
しかし、中小企業は、大手企業と比較するとDXに関連する情報が届いていないために、そもそも「デジタル化」や「DX」のメリットを知らず、当事者意識を持ちにくい環境にあります。
また中堅企業では、DXを推進する中核人材不足の課題もあると言われています。
まずは情報を収集し、自社の現状を分析したうえで身近なことから小さく始め、成功体験を積み重ねながら自社に必要なデジタル技術活用を推進することが大切です。
中小企業におけるDXの実態
中小企業における DX の取組状況としては、段階 1(デジタル化が全くの未着手の段階)、もしくは段階 2(デジタイゼーションの段階)11が全体の約 3 分の 2 を占めている状況であり、中小企業における DX の取組が進んでいるとは言えません。

出典:「DX支援ガイダンスー デジタル化から始める中堅・中小企業等の伴走支援アプローチ ー」(経済産業省, 2024年3月27日, p.11)
DX への取組段階と労働生産性・売上高の変化の調査からは、特に段階 3(デジタライゼーションの段階)及び段階 4(DX に取り組んでいる段階)の中小企業は着実に労働生産性や売上高を伸ばしていることがわかります。
高度なデジタル化や DX に取り組むことは、会社の価値を高める確かな手段であることが明らかになっています。
また、段階3と段階4の間にも大きな差があり、単に業務プロセスを効率化するだけでなく、デジタル化を通じた新たな価値の創造が重要であることが示されています。
DX はデジタルツールを導入したら終わりではなく、業務改善、効率化、生産性向上、売上増といった段階を踏みながら、企業として成長を追い続けるものです。
つまり、デジタル化とDXは連続的で、事業環境の変化に対応して経営を変革していく息の長いプロセスということです。
まずデジタル化に着手し、DX に取り組むための第一歩を踏み出し、そこから中長期的にDXの実現を目指すことが重要になります。
「まずは身近なデジタル化から取り組んでみる」という意識と、そこで得られた成功体験の繰り返しが、最終的にDX を成功させる上でも有益です。
.png?width=570&height=290&name=DX%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%81%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%94%9F%E7%94%A3%E6%80%A7%E3%83%BB%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%AB%98%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96(2015%E5%B9%B4%E3%81%A82021%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%AF%BE%E6%AF%94).png)
出典:「DX支援ガイダンスー デジタル化から始める中堅・中小企業等の伴走支援アプローチ ー」(経済産業省, 2024年3月27日, p.12)
まとめ
このコラムでは、DXの基本的な考え方や取組の段階について説明し、生産年齢人口が減少していく日本において、地方の中小企業にとってのDXの重要性について解説してきました。
まだデジタル化の初期段階にとどまっている企業もありますが、デジタライゼーションやDXの段階まで進めた企業では、労働生産性や売上高が着実に向上していることが確認されています。
こうした結果から、DXは単なる業務効率化にとどまらず、企業価値の向上に直結する重要な取り組みであることが明らかです。
大企業と比べて意思決定が迅速な中小企業こそ、変化に柔軟に対応できる強みがあり、デジタル化やDXの恩恵を受けやすいといえます。
まずは身近な業務から段階的に取り組み、自社にとって何ができるのかを見極めることが、DXへの第一歩となるでしょう。
私たち地方創生・フェアネス共創研究所は、デジタル技術を活かした地域課題の解決に取り組み、持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。
自社のDX推進について、外部の視点や専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ地方創生・フェアネス共創研究所にご相談ください。
出典
・「令和3年版 情報通信白書 第1部 特集 デジタルで支える暮らしと経済」(総務省, 2025年7月23日参照)
・「TOHOKU DX大賞2024 ビジネスイノベーション部門 優秀賞 デジタルを駆使したシン・働き方改革(株式会社髙梨製作所 山形県河北町」(経済産業省 東北経済産業局, 2025年7月23日参照)
・「情報通信白書 for Kids」(総務省, 2025年7月23日参照)
・「DX支援ガイダンスー デジタル化から始める中堅・中小企業等の伴走支援アプローチ ー」(経済産業省, 2024年3月27日, p.11-12)
・「2024年度版 中小企業白書 第1部 第4章 第7節 DX(デジタル・トランスフォーメーション)」(中小企業庁, 2025年7月23日参照)